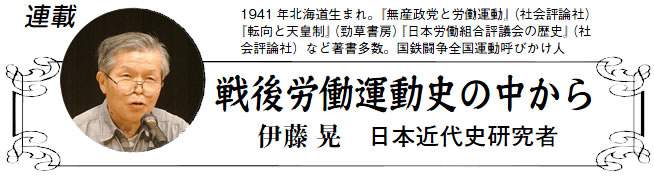
戦後労働運動史の中から第33回
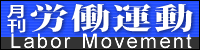
一九六〇年代 鉄鋼労連の敗北(1)
一九五〇年代総評所属の有力な左派産業別連合体に鉄鋼労連がありました。ところが七〇年代に入るころ、鉄鋼労連指導部から左派(社共両党員)は一掃され、右派組合に変貌していました。これまでお話してきた五〇年代、大争議の過程で第二組合が生まれ、やがて第一組合が衰滅するという右派化がよく起こりましたが、六〇年代には大組合の執行部が選挙を通じて右派に乗っ取られるというケースが増えました。鉄鋼や造船などに多かったが、鉄鋼では労連全体として右派化したわけです。この間、右派労連を集めてIMF・JC(国際金属労連日本協議会)が作られ、鉄鋼労連は総評に留まりながらその中心になる。このIMF・JCはのち連合結成の推進に貢献します。今回は、この右派化がテーマです。
以前、尼ヶ崎製鋼、日鋼室蘭の争議を取り上げたとき、鉄鋼産業の合理化にふれました。今回も問題はやはり合理化関連、ただし、この産業の最大企業、八幡製鉄、富士製鉄(この二つが七〇年に合併して新日本製鉄になる)、日本鋼管にまで関わることです。
鉄鋼労連の戦闘性が大きく発揮されたのは五七・五九両年の賃上げ要求ストライキ。ところが、これがまた挫折の第一歩になったのです。五七年には一一波のストライキ、五九年にも全力の長期ストで戦いましたが、完敗に終わります。当時の日本資本主義は各産業とも急速な合理化が進み、飛躍期に入りつつあります。ここで重要だったのは、敗戦後資本と対等のつもりで我物顔にふるまう(と資本側は感じる)労働運動を決定的に押し返すことでした。いまは少し重みが減ったようにも見えるが、そのころ鉄鋼は自他ともに許す主導的産業、「鉄は国家なり」の自負心がある。使命感をもって労働運動との対決に臨みます。
五七年には賃上げゼロ、五九年には最初の提示から一歩も譲らず押し切った。資本の側が一度決めたことは譲歩せず、こうして資本の権威を労働運動と社会に見せつけること、ここに狙いを定めていました。その強硬さはのちに「鉄の一発回答」ということばが生まれたくらいです。
鉄鋼労連側には一つの弱みがあった。最大最有力の八幡製鉄の組合がいつも統一ストライキから脱落しがちで、足を引っ張ったことです。ここでは「企業による合理化を組合が生かし、呼応していくべきだ」とする右派(そのリーダーが宮田義二)が強く、「硬直した」ストライキ姿勢に批判的だったのです。
しかし五七・五九年の敗北で鉄鋼労連左派が一挙に後退したのではありません。八幡でさえ、六〇年ころまで執行部選挙では左・右のシーソー・ゲームが演じられていたのです。問題はこのころ、各組合の内面で急速に空洞化が進行しはじめたこと。その原因は大手企業が競って進めた技術革新が新生産過程を担うべき労働者のつくり変えを伴っていたことです。鉄鋼労連はこれと十分に戦えませんでした。詳しい状況は次号で。
伊藤 晃(日本近代史研究者)