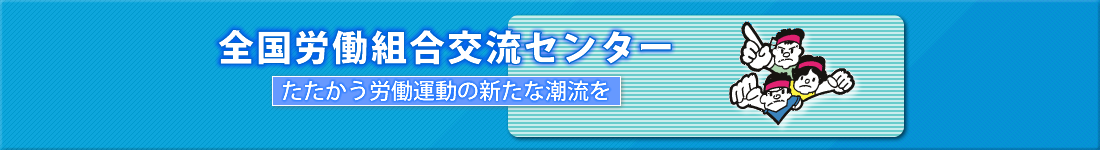戦後労働運動史の中から 第27回
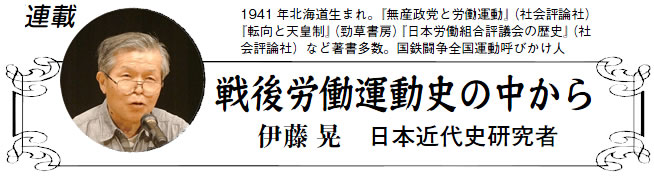
戦後労働運動史の中から 第27回
一九五七年国鉄新潟闘争(2)
(前号から続く)五七年春、情勢は緊迫してきました。国鉄当局は、仲裁裁定にもとづく給与支払いの期日を遅らせるなどケチな小細工を行い、一方、抗議行動への処分は遠慮なく出してきます。右派の分裂行動に悩む国労指導部の足元を見ての高姿勢です。実力行動にはもっぱら警察力を差し向ける。マス・メディアに「国民の足を奪うな」と世論操作をさせる。
しかし労働者たちの闘志は盛んでした。各地(特に広島、ここは革同系が強い)で本部指令を越えた行動を展開し、多くの列車が停まります。弾圧が激しいから長期低姿勢でと、ためらいがちな本部を、現場労働者が叱咤激励している形でした。一方で、右派の闘争批判も本格化してくるし、また全逓など、他の公共企業体組合は、処分はあっても解雇者がなかったから闘争は低調でした。
七月に入って、また五、六月の闘争に対する大量処分です。ここで一歩も引かない決意をみせたのが新潟地方本部でした。ここも革同派の拠点です。多分、左派をねらいうちという意図があって、ここでは当局側も一段と強硬でした。すでに一地方の衝突ではなかった。
七月九日、新潟地本は「われわれは戦う。指令を出してくれ」と中央本部に要請。他地方の低調と本部の微温的な指令を越えて、一〇日、全面的闘争に入り、数日間列車運行はほとんど停止しました。この間、派遣された中央本部員と当局側が交渉、処分撤回より処分軽減・先送りで落としどころを探る組合側に対し、当局側はカサにかかってくる。しかも交渉継続中、警察が組合員検挙で挑発します。
全国の耳目は新潟に集まりました。戦後最強の組合、しかもスト権を奪われて何年も耐えてきた国労の大爆発です。自分の地方を新潟に続かせることができず歯がみする思いの国労活動家、全国の戦闘的労働者は、ストライキ闘争とはこういうものだったと、戦後初期を思い出した感がありました。一方で「世論」を動員しての国労包囲攻撃も激烈でした。このときは農民が動員された。トラック輸送が未発達な時代で、農産物輸送は鉄道が頼りだったのです。当時、高校二年生だった筆者は、「スイカが腐る、ブタが死ぬ、農民の叫び」といった新聞の大見出しをよく覚えています。
国労中央部は、新潟闘争を全国に拡大する意志を持ってなかった。処分反対闘争は長期に粘り強くと言って、現地の収拾をあせります。やはり右派の策動が怖かったのです。結局一七日、現地から上京した代表を加えて激論の末、強引に闘争の中止を決定しました。こうして、労働者たちに戦いきったという気持ちを残せずに、闘争は終わりました。
組織の動揺を恐れての闘争中止でしたが、争議中に発生した新潟の第二組合は、争議後むしろ拡大し、東北地方を中心とした動きとともに、右派新組織の拠点になっていきました。
新潟闘争の与えた教訓は非常に大きかったと思います。これについては次回に私の考えを述べましょう。 (次回に続く)
伊藤 晃(日本近代史研究者)