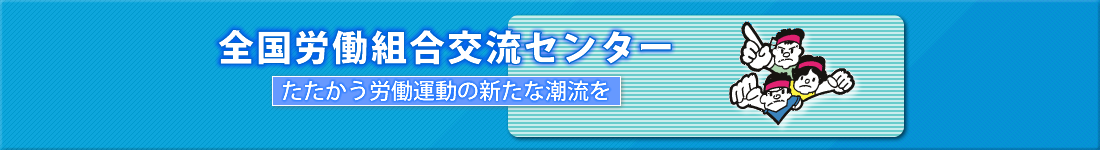戦後労働運動史の中から第32回炭労の闘争と三池争議(4)
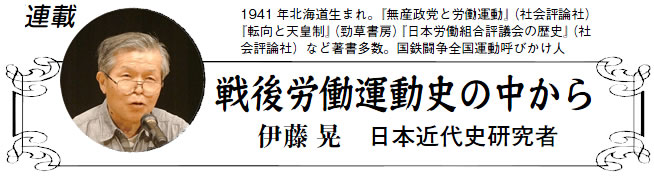
戦後労働運動史の中から第32回
炭労の闘争と三池争議(4)
(前号より続く)
三池でホッパー決戦が迫るころ、全国的には六〇年安保闘争が高まっていました。このなかで三池への支援も強まり、「三池を守る会」が全国に多数生まれたのもこの頃です。しかし総評・炭労指導部は、ホッパー決戦をやはり妥協のための取引材料にと考えていたフシがある。行き詰まった争議で「事件」を起こして社会を刺激し、仲裁を呼び込むきっかけにするのは、戦前の労働運動にはよくあったことです(仲裁者が官憲の場合もある)。
実際、政府が阿吽の呼吸でこれに応じました。六月に新安保条約は強行成立、岸信介内閣も退陣、代わった池田勇人内閣は「寛容と忍耐」などと言って反政府の空気を懐柔する。この内閣の労働大臣がまたしても石田博英だった。石田は、流血の激突は避けねばならないとして、中労委のあっせん乗り出しを働きかける。総評・炭労指導部も、少しはましなあっせん案が出ることを期待して「休戦」に応ずるのです。いわば武装解除です。
しかし結果は無残なもんでした。出されたあっせん案(八月)は、三池の職場闘争は労働運動として非正常と断じ、指名解雇を事実上全面的に認めたのです。三池労組はこれを拒否するが、炭労は臨時大会ををくり返して激論の末、結局九月に入って受諾を決定しました。完全に包囲され、万策尽きた三池労組も、これに従わざるを得ませんでした。こうして二八二日に及ぶストライキは敗北を迎えます。
三池の敗北で総評は、職場闘争への自信を喪失し、また大企業でストライキを敢行する勇気も失いました。学者たちは、三池争議を戦後労働運動の高揚から下り坂への分水嶺とみなす。それは一応その通りだが、私たちはこういう評論に止まっているわけにはいきません。
本当は、炭労にとっての正念場はこの争議後にあったのです。合理化というものを考えると、その実質化が強行されるのはいわゆる「反合理化争議」が終わった後なのです。ここでその合理化の矛盾を突いて緊張した対抗関係を保ち、これを通じて団結を固める。「資本との非和解の反合理化闘争」とはこのことです。本当の勝負はここで分かれる。
三池においてもまさにそうでした。争議後、会社側の第一組合つぶしは激烈をきわめ、争議敗北後も崩れなかった第一組合はここで第二組合に多数を譲ります。また職場が完全につぶされ、会社は坑内の安全対策を徹底してサボった。六三年、五百人近くの労働者の生命を奪ったあの大炭塵爆発事故はこの結果として起きたのです。そしてこの頃、全国のヤマで大小無数の事故が相次いでいます。炭労はここでこそ抗議の声を上げて闘争に決起すべきでした。しかし、抗議の声は上げたけれども闘争はなかった。総評・炭労はその頃、炭鉱離職者のための雇用政策(このこと自体は必要だったが)を政府に要求することに専念していたのです。なお、炭鉱で働く何万もの労働者の命を守る戦いをつくれなかった、ここに炭労の本当の、かつ最終的な敗北がありました。
伊藤 晃(日本近代史研究者)