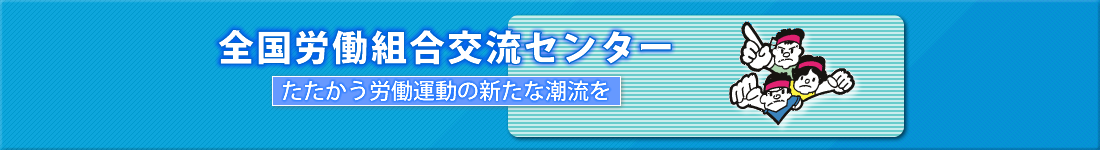労働組合運動の基礎知識 第44回 8時間労働制解体のための変形労働時間制

労働組合運動の基礎知識 第44回
8時間労働制解体のための変形労働時間制
※8時間労働制解体のための―労基法32条の2(1カ月単位の変形労働時間)
変形労働時間制が導入されたのは1988年。国鉄分割・民営化攻撃以降のことである。ただし、1947年に労働基準法が施行されて以来、現実には就業規則において4週間を平均して1週あたりの労働時間が上限(当時は48時間)を超えない定めをしたときは、特定の日又は特定の週において労働時間の上限を超えて労働させることができることとし(4週間単位の変形労働時間制、施行当時の第32条2項)、多くの企業がこの方法を採用していた。
1988年に4週間単位の変形労働時間制を発展的に解消し、新たに各種の変形労働時間制を導入した。具体的には、一定の期間(変形期間)を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間(現行法では40時間、特例事業の場合は44時間)を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えたり、特定の週に法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとして扱う(三六協定の締結・割増賃金の支払いが不要になる)。ただし、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない(昭和63年1月1日基発1号、平成3年1月1日基発1号)。
具体的には、1カ月単位の変形労働時間制の場合は、28日160.0時間。29日165.7時間。30日171.4時間。31日177.1時間の範囲内というように、各日、各週ごとに労働時間を振り分ける。
そうして就業規則に「始業時間が1日~24日までは9~17時(正午から13時で休憩)、
25日~月末までは9~19時(正午13時まで休憩)といったように記載する。
1カ月単位の変形労働制の導入はこのように、具体的に就業規則に記載しなければならない。したがって別個に1カ月単位の変形労働時間については労働基準監督署に提出する必要もない。
変形労働時間制と言っても、就業規則で定めた労働時間を変動することはできない。例えば、7時間と所定労働時間で定められて日に、8時間働いてしまったからといって、「翌日の所定労働時間を1時間減らして残業していない」ということにはできない。
7時間が所定労働時間の日に8時間働いたのであれば、1時間残業したことになるし、10時間の所定労働時間の日に10時間働いても、残業をしていないことになる。仮に所定労働時間以内に退勤したのであれば、早退扱いになる。
この変形労働時間制を悪用して毎日始業・終業時間を変更するようなことが行われている。上記のように就業規則には8時始業、終業17時のところ、「明日は6時始業。終業15時」と前日に通告し、始業終業時間を変えて残業代を支払わないやり方をしている企業がある。
ネットで検索すると、司法書士や弁護士は「業務の都合により就業規則に始業終業時間を変更することがある」と記載すれば合法であるかのように書いているが、納得できない。
小泉義秀(東京労働組合交流センター事務局長)