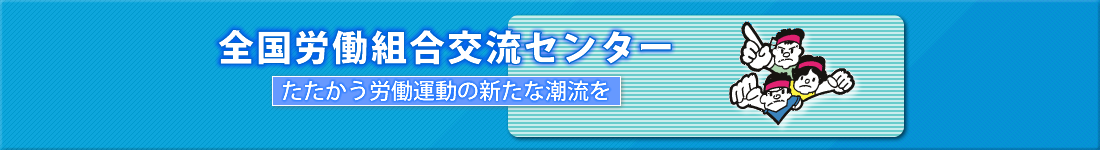戦後労働運動史の中から 第10回
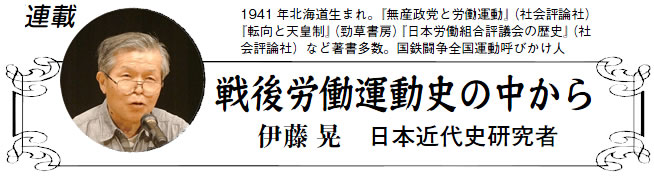
戦後労働運動史の中から 第10回
1949年、なぜ労働運動は敗北したか
1949年は労資激突の年でした。民主化の推進力とみえたアメリカ占領軍が、中国革命進展などアジア情勢変動で政策を転換し、経済面では、赤字財政・インフレを収束させ、諸企業を国家資金への依存から自立させる方針をとります(ドッジ・ライン)。この経済の「体質改善」は膨大な労働者解雇を生みました。民間の「企業整理」、国営企業の「行政機関職員定員法」による国鉄10万人、郵政2万9千人の解雇など、この年の失業者増は政府の計算でも50万人、実際はその倍くらいだったかもしれません。
大ストライキ闘争が予想されるところでした。しかし結果をみれば、解雇反対闘争はほとんど不戦敗に終わりました。上昇を続けてきた戦後労働運動は一気に混迷に陥るのです。なぜこんなことになったのでしょうか。
労働者の闘争意欲はあったのです。国鉄は大量解雇準備のねらいで6月に新交番制を実施しますが、これに対して東京・神奈川の電車区・車掌区では激しいストライキで応じます。東京交通労働組合(都電・都バス)は、折から企てられた都公安条例に対して左派系支部がストライキで戦います。ところが、肝心の指導部が消極的でした。右派はもちろんですが、左派を代表する共産党がむしろ火消しにまわったのです。国鉄の解雇反対闘争に対して、ストライキは支配階級の挑発だと。
共産党は当時、強権的態度に出て、あらゆるストライキに中止を勧告・命令で介入する占領軍権力を恐れたのかもしれない。ずっと占領軍の好意を力にしてきた受動性の裏返しと言えるでしょう。戦うべきこの決定的段階で自派系労働組合を「温存」し、多様な戦術で諸地方権力に人民運動を対抗させる闘争(地域人民闘争と呼ばれた)に動員しました。地方権力をマヒさせれば中央権力の基盤がゆらぎ、革命につながるという理屈です。もちろんただの理屈で、戦闘的労働運動を資本の正面から遠ざけ、分散させただけに終わりました。
権力はこの間、問題の本質を見すえていました。下山・三鷹・松川と続いた怪事件をフレーム・アップに有効に使って、戦う労働者と民衆とを離間する。労働者が萎縮するなかで、国鉄でも郵政でも狙った大量解雇は難なく成功しました。忘れてはならないのは、このとき活発な活動家がごっそりと職場から逐われたことです。大量解雇はレッド・パージを兼ねていたのです。
民間企業でもたいして事情は変わりません。左派の拠点だった東芝では、このころ右派が台頭し、抗争が続いていますが、左派はやはり地域人民闘争に力をとられ、ストライキ闘争に集中できない。結局、主力工場では自主退職者が続出して、これで企業側の解雇予定人員が埋まってしまう。労働者が組合に信頼を失って、それぞれ個人的に自分の身のふり方を考えるようになっていたということです。
戦後資本主義再建の一大課題は、活発な労働運動の火を消すこと。支配階級は1949年、これに一旦は成功したのです。
伊藤 晃 日本近代史研究者
1941年北海道生まれ。『無産政党と労働運動』(社会評論社)『転向と天皇制』(勁草書房)『日本労働組合評議会の歴史』(社会評論社)など著書多数。国鉄闘争全国運動呼びかけ人