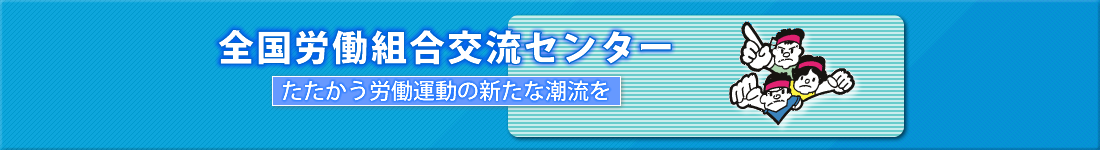■戦後労働運動史の中から 第19回 1954年日鋼室蘭争議(2)
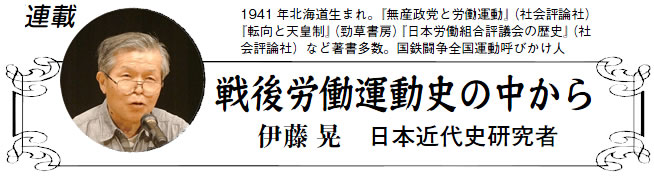
■戦後労働運動史の中から 第19回 1954年日鋼室蘭争議(2)
■戦後労働運動史の中から 第19回
1954年日鋼室蘭争議(2)
この中央委員会の情況は、人間の遺志形成を理性を内にもつ「個」の自由な判断に見る立場からは異様に見えたでしょう。状況を冷静に見る声が激情に駆られた群集の威迫によって、勝算もないのに否定されたのだと。しかし妥結方針は組合員の討議を経ない頭ごしのものだった。その拒否は争議の過程で集団的に形成された闘争意志の表現でした。「はじめから自分たちを信頼しない妥協は納得できない」と。
激情を強固な団結に形成する条件もあった。中委決定は組合員の全員大会でも確認された。それを見ていよいよ発足した第二組合の攻撃的行動にも渾身のピケで対抗し、第一組合は争議終了時でさえ多数派を維持していました。
不利な状況は確かにあった。鉄鋼労連はもともと弱い組合だと思っているから指導に自信がなく、もう腰が引けています。争議を鼓舞してきた総評高野実事務局長も、数々の争議の失敗を批判され、十分な身動きができない状態です。そして総評・鉄鋼労連の支援なしでは、資金面でも長期の争議維持は困難だったでしょう。いずれにせよ組合員が自分の意志で行動を決める必要がありました。
組合指導部はもう一つ疑問の決定をしました。ピケが部分的に破られ、わずかながら生産が再開されると、こちらからピケを解いて、主力の青年労働者を全国宣伝活動に派遣したのです。現場の団結を固めるより闘争を「全国化」する。これは争議の実情を知らせて共感を呼び起こす上で効果はありました。けれどもこの頃から、その指導部の頭越しに、総評上部による中労委を引き出しての調停工作が進んでいたのです。妥結するなら労働者の過半数を保っている今のうちだと。現地に相談なく、8月の会社提示よりさらに幾分譲歩した解決案が作られます。指導部はこれを知らされるが、やはり広く討議しようとしない。結局組合員は、これは決まったことだと、受け入れか否かだけを問われたのです。
不満が渦巻く現地に高野実が自ら説得に向かいます。彼は誠意をもって話し合いに臨み、組合員や主婦たちを同意させました。しかし、職場に戻って第二組合の労働者との再統一をはかれという高野の言葉は、組合員には空しく響いたでしょう。こうして662人解雇をもって争議は終わりました。
職場に戻った組合員を職制の激しい攻撃が待っていました。会社・第二組合の連携で勢力回復の道は阻まれます。それはわかっていたことです。それとどう戦うのか。争議終了に当って議論し、意志統一しなければならなかったのはこのことです。それが十分になされたとは思えません。この争議は終始、指導に問題があったというべきでしょう。翌年、労働者の過半を第二組合にとられたことで、組合員を責めることはできません。翌年、つまり1955年は高野実に代わって太田薫・岩井章が総評指導部を握る年です。この指導部にとって、日鋼室蘭争議はただの悪夢だったのかもしれません。
伊藤 晃(日本近代史研究者)