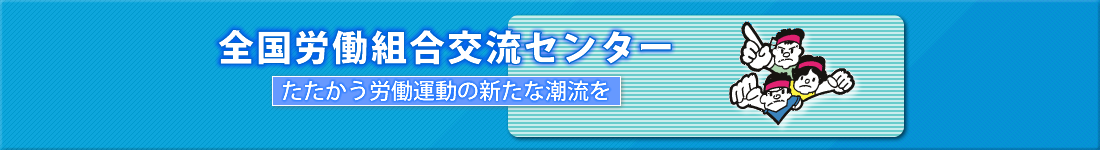戦後労働運動史の中から第26回
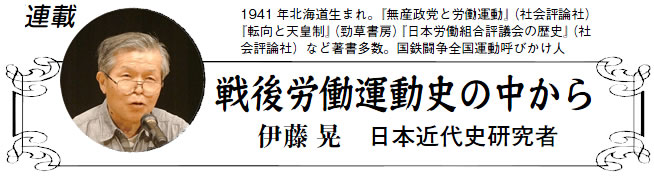
戦後労働運動史の中から
第26回
一九五七年国鉄新潟闘争(1)
国鉄分割・民営化までの国鉄労働者は公共企業体労働者だということで、一九四八年以来ストライキ権を奪われています。その代わり給与等について調停・仲裁機関を置き、その裁定を政府・当局は必ず実施することになっていました。ところがその裁定が種々の口実で完全実施されない。国鉄労働組合(国労)に結集した労働者はこれに怒り、順法闘争、休暇闘争などの実力闘争で対抗していました。当局側はそれを違法の争議行為だとして大量処分を繰り返します。組合側は当然実力闘争で反撃する。これにまた処分が来る。こういう状況の中で双方が激突したのが一九五七年七月国鉄新潟闘争でした。
この年は岸信介内閣が成立した年です。この内閣で労働大臣を勤めたのが石田博英。自民党労働政策に名を残したこの人は、闘争と処分のいたちごっこを終わらせるべく国労に立ち向かいます。お互いに法を守ろう。政府は仲裁裁定に従うことを約束する。その代わり組合は絶対に争議行為をするなと。石田はリベラル派で知られた人。しかしリベラルとは、資本主義の根幹を守ることにおいて最も戦闘的ということでもある。彼は「法に基づく」処分については一歩も譲らなかった。
一方、国労の方も実力行使から引くことはできなかった。それは多数労働者の意志であったからだ。そしてこの戦法をとれば、必ずダイヤは乱れ、事実上のストライキになる。一般組合員に及ぶ処分が来るが、その中でも国労が頑張ったのは、組合員が指導部を強く押し上げていたからです。スト権を奪われてから十年近いが、彼らはスト権は自分たちの当然の権利だということを忘れてはいない。しかもスト権剥奪の代償、賃金は「公正に」決めるという、それは破られっぱなしです。労働者たちの怒りは根深いものがありました。彼らは実力行使を、言葉では言わないが、実際上ストライキになることを承知で行っていたのです。政府がまさにストライキ権に神経をとがらせる中で、労働者たちはストライキ権を政治的対決点に押し上げていったのです。
ただ、国労には大きな悩みがありました。この組合は創立時から左右の抗争が激しく、共産党系と民主化同盟(民同)派が対立しましたが、四九年に共産党系が後退した後、今度は民同派が左右に割れ五七年当時は、主流の民同左派に対し、右派の新生民同派が一大勢力をなしています。さらにもう一つ革新同盟(革同)派というのがあって、これが主流の民同左派の左に位置していました。実力行使を続ける時、最も戦闘的だったのは革同派。一方、右派は実力行使に大反対。組合中央本部の闘争指令に対して、これを分会ごとに返上、あるいは黙殺して拒否するのです。主流派の本部はこれをまとめきれず、むしろ分裂含みの右派を刺激するとまずいから無理はできないというのが本音でした。しかし五七年には非現業職員のあるいは職能意識を利用した分裂組織づくりがぼつぼつ始まっていました。
(次回に続く)
伊藤 晃(日本近代史研究者)