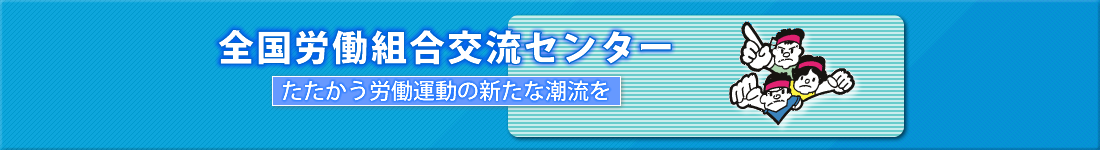関生支部の闘いとユニオン運動 第3回
産業別統一闘争の合言葉―「一人の痛みはわが痛み」
関西生コン支部は、セメント大資本が敵であることを自覚し、そこから産業別組合の方向で陣容を整えていきます。七三年の集団交渉が実現する以前、それは支部が産業別組合を確立する前段階でした。ここで、企業別組合の連合体から産業別組合へ向かう模索と試練の闘いがありました。また、この時期の運動と組織は、生コン支部だけではなく、日本の労働運動にとっても注目すべき時期でした。それは日本で産業別組合をどのようにして確立すれば良いのか、その先陣の位置にあったからです。
産業別組合へ向かう闘いで関西生コン支部が獲得した貴重な教訓は三つあると考えられます。組織と運動路線と精神です。
その第一は、産業別統一指導部です。この点はのちに詳しくふれますが、個人加盟組織であることもさることながら、より重要なことは労働組合の権限を支部に集中したことです。
関西生コン支部の前身は一九六〇年の「大阪生コン輸送労組共闘会議」(生コン共闘)でしたが、この組織は企業別組合の共闘組織だったのです。これを基礎に一九六五年に関西生コン支部が結成されました。支部はその結成当初から、交渉権、争議権、妥結権の権限を支部執行部に集中する組織体制を確立したのです。この時点ですでに、関西生コン支部が産業別組合であることの特質の一つを、獲得したことになります。この体制がその後の産業別統一闘争の戦闘司令部の役割をはたすことになるのです。
支部結成から七二年、七三年にかけて、支部が獲得した教訓の第二は、産業別統一闘争の運動路線でした。それは産業内の対企業闘争を徹底して闘い抜くという路線です。それは単産の争議支援とは少し違います。争議支援は個別の企業別組合の争議に単産に加盟する企業別組合が支援する方式です。この間の生コン支部の運動は、個々の組合どうしの支援ではなく、産業内の一企業に対する産別組織あげての闘いなのです。
武建一委員長は当時、こう述べています。「職場では一人であっても労働組合の存在を認めなさいと、会社に求めていく。拒否すれば、一人であっても、それを支援するために全員の動員をかけて、その会社に抗議行動をしていく。組合員が一人もいない工場へも抗議、宣伝をする。そして、生産点を完全に止めてしまう。そういうことをずっと繰り返していました」
これを産業別組合の運動に普遍化して表現すれば、産業別組合が規制する産業別労働条件の基準を破る企業、あるいは基準に加わらない企業、それらの企業に組合員がいようが、いまいが関わりない、ということです。その企業は、産業レベルでは闘争相手とみなさなければなりません。
この運動路線は、いわば産業別〝動員主義〟という方法で遂行されました。この〝動員主義〟は、のちに議論になるところであり、あとでふれますが、それは組織をあげて、直接的な抗議行動を集中的に展開することです。紛争があった工場に動員する、あるいは紛争と関係のない工場でも動員して生産をストップさせる。親会社のセメント・メーカーの工場に動員をかける。工場の泊まり込み闘争、工場再開阻止のためのプラント打ち壊しの阻止の闘いなど、動員にもとづく集中的な行動がありました。
〝動員主義〟という言い方には、批判的なニュアンスがありますが、さきほどの産業内の個別紛争を、組織の総力を挙げ、力を集中して闘う方法としては、当然のことです。このような産業別闘争によって、この時期、関西生コン支部は注目されるようになりました。武委員長は「『生コン支部のような運動をしたら強い、われわれはああいう方式を求めているのだ』と言われるようなものをつくる闘争でもありました」。「〝暴力団よりも強いらしい〟ということになったのも、この時期です」と述べています。
支部が獲得した第三の教訓は、産業別連帯の闘争精神です。自分が雇われていない企業であっても、労働者が踏みにじられていたら、身体を張ってでも支援する。このなかで、関西生コン支部は、産業別統一闘争をたたかう戦闘部隊に成長していったのです。だからこそこの時期に、あの関西生コン支部の言葉が、合い言葉のように根づいていったのだと思います。それは「他人の痛みはわが痛み」です。自分の企業でないところで労働者が抑圧されていれば、それは他人事ではなく、「わが痛み」としてとらえ支援する。この産業別闘争の精神にふさわしい言葉でした。
この言葉は生コン支部がつくったのではなく、他でも使われていました。しかし、この言葉の真意は、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」のような単なる相互扶助・博愛主義ではないように思います。
「他人の痛みはわが痛み」との言葉の由来は、私はわかりませんが、それと関連している言葉は昔から欧米の労働運動にありました。
写真は、一八八九年のロンドンドックの大ストライキのあと次々に一般労働組合は作られ、その一つの組合の組合旗です。左の方に書いてある言葉が「一人に対して傷つけることは、みんなに対して傷つけることだ」(An injury to one is an injury toall)です。そして右に「我々は闘う。そして死ぬだろう。しかし、決して屈服しない」(We will fight and may die. But we never surrender)と書いてあります。戦後のアメリカでも、労働運動の後退を描いた本がありますが、その題名は「すべてにたいする攻撃」(An Injury to All)でした。
関西生コン支部が獲得した「一人の痛みはわが痛み」は欧米の戦闘的労働運動の合い言葉と通底しています。産業内の「一人の痛み」も、統一闘争で「わが痛み」として闘うという精神だと、とらえることができます。
集団交渉がまだ実現していない時期に、産業別統一闘争と、それを支える戦闘的な精神を、関西生コン支部が獲得した意味は大きいと思います。
この力が次の段階を切り開いていったのです。
木下武男(労働社会学者・元昭和女子大学教授)
『月刊労働運動』2020 年6月号