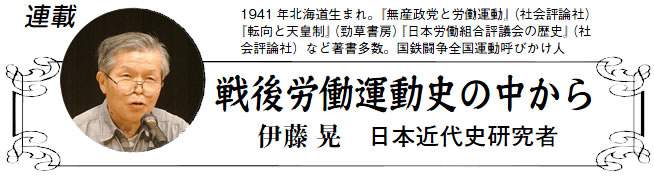
戦後労働運動史の中から
一九五七年国鉄新潟闘争(3)
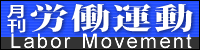
(前号から続く)
国鉄新潟闘争は、「徹底して戦うと組合が割れる」という当時の「定型」に、また一例を加えたかに見えました。左派と目されたリーダーもそこから教訓を感じたでしょう。「観念的に急進化して、また労働者の一時の感情に乗って無理をしてはだめだ」。
だが、ここで忘れてならないのは、新潟闘争は左派の「構想」が大衆感情を「動員」しただけのものではなかったということです。
国鉄労働者には、前にお話したように、生きる権利をないがしろにされることへの広い怒りがあった。政府・当局は、四八年以来、彼らをさんざん痛めつけて、運動の骨を抜いたつもりだったが、戦う労働者の誇りは死んではいなかった。順法闘争をやって列車を停滞させ、実際上ストライキになっても、その十年前、それは当り前の状態だったのです。
だから問題は、労働者たちに現存する戦う意志にふさわしい行動の形をみつけることだった。徹底した討論とそれによる一致した行動が、労働者たちに、この戦いはわれわれの意志によるわれわれの戦いなのだという確信を与えるでしょう。団結はこの確信の上に積極的・攻撃的に作られるのであって、退いて分裂行動から組合を守ることでは作られない。
新潟闘争の敗北は、現地労働者の戦う意志を沮喪させ、分散させました。その最大の原因は、自分たちのことを自分たちで決められず、決定権が中央に移されて、現地労働者の意志の外で事が決まってしまったことではないでしょうか。孤立した戦いは確かに不利に傾いていた。だがそこでどうするか、それを戦っている労働者が議論し、自ら判断するのでなければならなかった。「ここは退く」。彼らがこう決断したとき、「戦いきった」という気分を残して闘争を一時収束させることができたでしょう。
だが国労中央にとって、そういう「高度な判断」は中央のみが負うべきものであった。理性は指導部にあり、一般労働者は感情で動くと思っているから。新潟へ派遣された中央オルグは、労働者の討論の中に飛び込んで、中央の見方を率直に伝えて議論するより、当局との交渉に目的があったようであった。
国労中央の任務はどこにあったか。それは労働者たちが当然のこととして戦っている実力闘争を一貫させ、ストライキ権のはっきりしたスローガンに高めることだったでしょう。
そして、公務・公共企業の労働者にストライキ権がないのはおかしいという気持ちは、当時戦う労働者の常識で、消えていない。その共感を盛り上げるために総評組織を全力で動かし、「国民的世論」に対抗すること。その力が及ぶか及ばないか。この情勢を現地の労働者とともに判断し、ともに決断すること。
戦いに退却はある。だが頭のよい人の作戦であっても、前線の労働者たちの意志が崩れるなかでの退却は、往々にして潰走になるものなのです。団結の崩壊がそれに続く。労働運動史の教訓がここにあります。
伊藤 晃(日本近代史研究者)